国立でみつけた自由な生きかた

誰もが自由で、人と繋がることができ、幸せを感じられる暮らしの場がまちに増えていくように。
東京・国立で家族と一緒に暮らしている土屋一登(つちや・かずと)さんは、双極性障害という生きづらさを抱えながら、「自由」を求めて仕事や生き方を見出していきました。
国立で出会った自由な人たち

生きづらさの当事者として、自分が掲げるテーマや想いをオープンにしながら、自由に暮らしや仕事を作ろうと本格的に考え始めたのは、国立に来たことがきっかけでした。
「高円寺のNPOで働いていた頃、同じNPOに勤めていた妻が『すごく雰囲気がいいまちだから住んでみよう』と国立に住むことを提案してきたんです」
長く住むつもりもなく、軽い気持ちで転居して、2020年に子どもが生まれます。同時期に土屋さんと勤務先NPOとの契約が終了し、次の仕事を探しはじめました。英会話教室の講師になろうと考えますが、どうもしっくりこず。そんな時、国立には組織に属さず、個人で活き活きとはたらく人の姿が多いことに気がつきます。

「育休中の妻に頼みこみ、就職活動の代わりに2週間、国立の街歩きをさせてもらいました。人づてに勧めてもらったお店に行ったりする中で、国立駅前の『国立本店』や、谷保のシェア商店『富士見台トンネル』、市内でNPO・市民活動をサポートする『プラムジャム』などに行き、そこに国立ならではのコミュニティが存在していることに気が付いたんです」
お店を持たずに、シェア商店でコーヒーやチャイを売る人、自宅で仕事をしながら、コミュニティスペースでまちの人との交流を楽しむ人。そこから広がっていく人との縁や仕事。国立のまちの中には、そこにしかない独自の経済や交流から生まれる、自由で自然な循環があるように見えました。
「自由に仕事ができるいろんな選択肢があって、自由に生きることができる。そんな自由な選択をする人たちが、国立に集まっていました。自分にもフリーランスのような働き方ができるかもしれない。すごく背中を押されました」
誰もが幸せに生きるまちへ

土屋さんは、2022年に『一般社団法人眞山舎(さなやまや)』を立ち上げ、これまでに培ってきた資格や経験を活かして、NPO・市民活動団体の寄付集めなどの相談を受けたり、自治体主催のNPO・市民活動団体向け講座の講師を務めるなど、ファンドレイジング支援(民間非営利団体向けの資金調達支援)を行うようになりました。2023年からは、「まちで何かをはじめたい」人のための連続講座『クラブサバーブ』のメンターも務めました。
また、自らも双極性障害という生きづらさを抱える当事者として、文部科学省「学校卒業後における障害者の学びの支援推進事業」を受託し、『リカバリーの学校@くにたち』を国立市公民館と連携して運営。同じ生きづらさの当事者だけでなく、さまざまな立場・バックグラウンドの人が対話的に学び合っています。
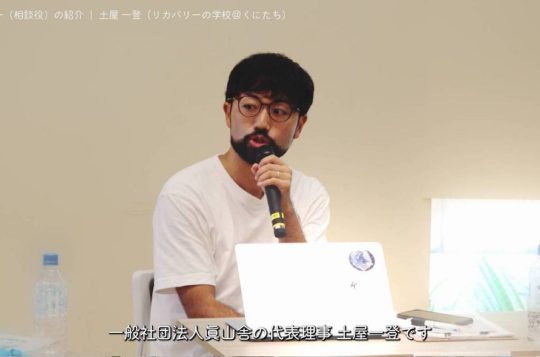
自由に生きる人が多い国立には、NPOや地域活動団体も多く、その相談役として土屋さんの存在は知られていくようになりました。
「今の夢は、生きづらさの当事者にとって生きやすい街を作っていくこと。僕は双極性障害を発症してからも、自分の想いを大切にして、自分には何かができると思い続けてきました。想いを発信するからこそ、共感しあえる人とつながることができて、大変な時でも人に助けられながら生きてきました。自分のような生きづらさの当事者が、自由で幸せを感じながら生きることができるまちは、きっと誰もが幸せに生きることができるまちだと思うんです」
誰もが自由で、人と繋がることができ、幸せを感じられる。そんな全ての人にとって生きやすいまちを作っている人や組織、団体のことを、土屋さんは『ローカルNPO』と呼んでいます。
生きづらさを抱える人、ローカルNPOと共に生きやすいまちをつくりたい。
その想いを持ちながら、土屋さんは今日も国立のまちを自転車で駆け抜けていきます。
Profile
- 名前
- 一般社団法人眞山舎(さなやまや)代表 土屋一登
- HP
- https://www.sanayamaya.org/
「ローカルNPO」とは
わたしたちの想いや願いを自由にカタチにする、"ローカルNPO" 。
